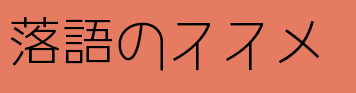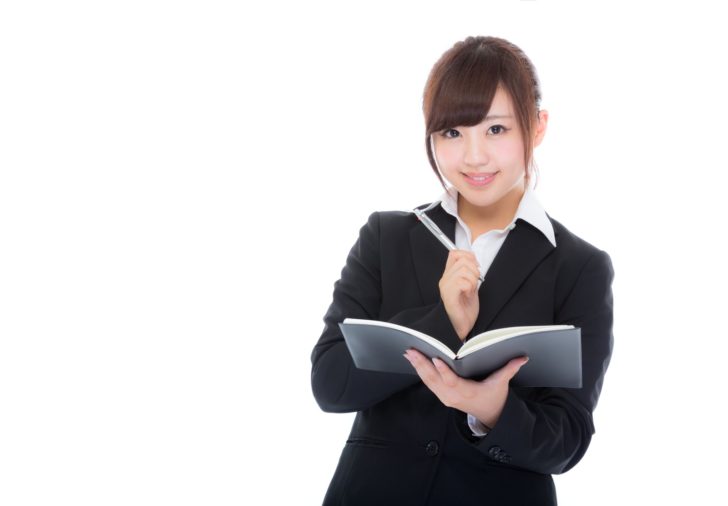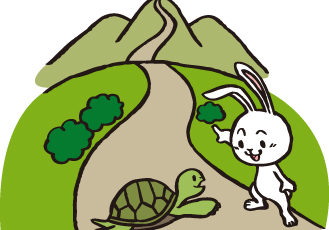落語を聞く手段はCDやDVD、テレビやYouTubeなど現代では様々な方法があります。
確かに私も落語のCD、DVDはかなりの枚数持ってますし、iPhoneを使って移動中に落語を聞いていたり、落語は身近なものとなっています。
しかし、落語を最大限に楽しむという事を考えるとやはり寄席で落語を聞いて欲しいというのが落語ファンからするとあるのです。
ただ寄席というのは、行った事の無い方からすると敷居が高く足を運ぶ気にはとてもならないと思うのです。(私もそうでしたから。。)
本日は、寄席というものが一体どうゆう所なのか?少しでも壁を取り除けるように解説したいと思います。
ホール落語と寄席は違う
まず、生で落語を聞きたいと思った時に、ネットで検索してみると全国のホール(会場)で様々な落語家が落語を披露おり、チケットが販売されているのが目に留まると思います。
これはいわゆるホール落語と呼ばれているもので、仲のいい落語家さんが二人で主催する「二人会」や個人で主催する「独演会」一門で主催する「一門会」などその形態は様々です。
実は私、寄席からデビューした訳ではなくて、初めて生で落語を聞いたのはホール落語でした。
というのも、ホール落語はチケットが事前に売っていて、席も決まっています。初心者にとってやはり安心感があったのです。
そしてもう一つの理由があって、その当時見たかった落語家さんは寄席には出演する事が無かったという事情もあります。
何故、見たかった落語家さんが寄席では見られなかったのかは、以前記事にしてますので、こちらをご覧下さい。
寄席とは?
寄席は、アーティストのライブのようなイメージのホール落語とは違い、年中無休で落語を聞ける言わばおじいちゃんの家のようなイメージなのかもしれません。
私も、初めて寄席に行った時には、こんなフランクなの?と驚いた記憶があります。
横では合間に弁当を食べてるお客さん、アルコールがOKの寄席であれば酒を飲みながら落語を楽しんでるお客さん。堅苦しい事は何もありません。
昼の部・夜の部
基本的に寄席は昼と夜の二部制になっているのですが、その間も入替する事もないので、全部見ようと思えば一日楽しむ事が出来ます。
もちろん、高座の最中はマナーとして出入りはしませんが、好きな時間に入り好きな時間に出れます。
なので、お目当ての落語家さんが見れたから途中で帰るなんて事も普通にあるのです。

寄席の流れ~入り方から出方まで~
寄席に入るのに事前にチケットは買うなんて事は基本ありません。
当日、寄席の木戸(入口)でチケットを買います。(この入場料を木戸銭と言います)
そして中に入ったら空いてる席に座るだけ。。ほんとこれだけです。(簡単でしょ?)
落語は前座から始まり二つ目へ
開口一番は前座さんからスタートします。分かりやすい古典落語を披露してくれますので、初心者の方も安心ですよ。
未来のスターを見れるチャンスでもありますので、是非、開口一番から見て頂きたいです。
そして前座の高座が終わると二つ目が登場です。やはり二つ目ともなると違うなぁ~と感じるんですよね。これがまた感動するんですよ。
ついに登場!真打!
二つ目の高座が終わって登場するのが、お待ちかね真打。
爆笑、爆笑。大いに笑って下さいまし。落語の醍醐味は当日、何の演目をやるか分からないところ。真打が一体どんな噺を披露してくれるのか?これが楽しいんです。
そして色物へ
寄席には、色物と言って、マジックや漫才、三味線のような音楽が間に入ります。(笑点を見てる方ならイメージが付くかと思います)
落語って聞いてる方も頭を使うんです。だから脳を休憩させる為に一呼吸置くために色物があるのかな?と個人的に思います。
そして大トリへ
色物が終わると、落語、そして落語、そして色物といった流れで進みます。
そして昼の部の最後に高座に上がるのが大トリ。もちろん有名な落語家さんが出るのはここです。是非大御所の名人芸を堪能して下さい。
そして夜の部へ・・・
終わりに
簡単な流れで説明してしまいましたが、寄席は実際行ってみると意外に気軽に行けるとこなんだって思うと思うんです。
敷居が高く感じるのはイメージなだけ。時間空いたから少し落語でも聞いてくか!こんな感じで立ち寄れる場所なんですよ。
そして最後に一つ。もし、寄席に行ったら注目して欲しい事があります。
落語家さんは、当日何の演目をやるか決めるのです。当然、夜の部の大トリともなると、それまでに15人以上落語を披露しています。
事前に打ち合わせなど出来ないですから、当日、それまで披露された演目は何かをチェックし、前の人が滑稽噺をやったから、最後は人情噺でいこうとか、マクラを話しながらお客さんの顔色を見ながらそこで演目を決めるとか、大トリを務める落語家さんは、レパートリーが豊富にないと務まらないのです。
真打の中でも寄席の最後を締めくくる名人の落語。是非味わって頂きたいです。