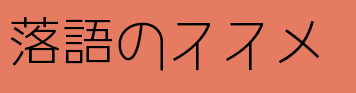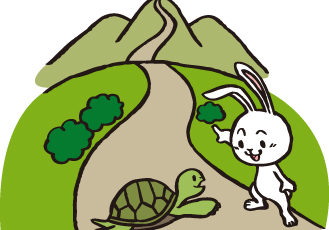「三方一両損」落語を知らない方でも聞いた事がある言葉かも知れませんね。中には三方一両損をもじって三方一両得なんて使われ方もする事もあったりして有名な言葉ではありますが、実際は落語の噺です。
三方一両損って言葉は知ってるけど、どうゆう話かは知らないって方は多いと思いますので是非ご覧になって下さいね。
古典落語 三方一両損
古典落語には政談と呼ばれるものが多くあります。簡単に言うと「お裁きもの」ですね。この三方一両損は江戸っ子の典型を扱ったものになります。
神田白壁町の左官金太郎が、書付と印形、それに三両の金が入った財布を拾うところから物語は始まります。
中に入っていた書付から落とし主は神田堅大工町の大工熊五郎と分かった金太郎は届けに向かうのだが・・・
あらすじ
「おう、おめぇが大工の熊五郎か?」
『そうだが、何か用があんのか?』
「用がなけれりゃこんな小汚いところくるもんか。財布を拾ったから届けに来たんだ」
『そうか、印形と書付は貰っておくが、金はいらない。てめぇにやる』
「そんな金をもらうくらいなら、最初から届けねえよ」
『もとは俺の金かもしれんが、いったん懐から飛び出したんだ、褒美にくれてやるから帰りに一杯やれよ』
なんて言うもんだから、喧嘩になってしまったのだ。
結局、熊五郎の大家が止めに入ってようやく収まったが、面白くない熊五郎は今度は大家に毒づき始めた。怒った大家は南町奉公大岡越前守さまに訴えて白州の上で謝らせるから、今日はひとまず帰ってくれと言うので金太郎は引き上げる事にした。
ところが長屋に帰って、自分の大家に話すと向こうの大家の顔は立ったが俺の顔はどうしてくれんだ、と怒りだしたのだ。そして願書を書くから逆に訴えてやれという事になった。
双方から願ったものだから、すぐに奉公所から呼び出しがかかった。
黙って言い分を聞いていた名奉行大岡越前守、静かに口を開く。
「左様か。両名とも、しからばこの三両。いらぬと申すなら、越前、預かりおくがよいか?」納得する二人を見てさらに奉公は続ける。
「では、そのほうたちの正直さに、越前が一両足して二両ずつ褒美としてつかわそう」
奉公が一両出し、両人に二両ずつ褒美として与えたので、三方が一両の損で無事に裁きは終わり、越前の計らいで食事が出た。
「これこれ、いかに空腹でもあまり食すではないぞ」
『へぇ、多かぁ(大岡)食わねぇ』
『たった、一膳(越前)』
題名で古典落語のあらすじを検索出来ます!隠れた名作を見つけて下さい!
古典落語の名作はまだまだ他にも!