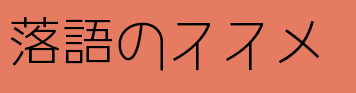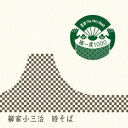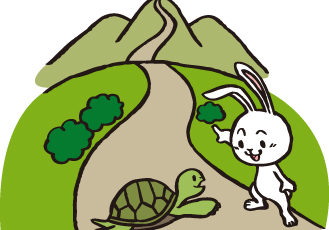本日も名作古典落語をご紹介したいと思います。本日のお話しは、古典落語の中でも特に有名なお話しですので、聞いた事のない方は是非聞いてみて欲しいです。
時そば(時うどん)
上方落語では時うどんとして演じられる事もある演目で、元は上方落語から始まり明治時代に江戸落語へ伝わり時そばとなったという話もあります。5代目柳家小さん師匠など、多くの名人が十八番としていた演目でもあり、蕎麦をすする仕草、音、名人芸を見る事が出来る演目です。
あらすじ
ある寒い夜のこと、屋台のそば屋にある男がやって来ました。
男は一杯のそばを頼みます。それからというもの、まぁよく喋る客。ありとあらゆるものまで褒めちぎるのです。屋号から割り箸、そばからちくわまで。そばを平らげ一通り喋った客はお勘定を頼みます。
「いくらだい」
「16文になります」と店主。
細かい銭しか持ってない男は、店主に手を出すよう言います。男は1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つと数えた所で、「今何刻だい」と店主に尋ねます。
店主は「今9刻でぇ」と返すと。
10つ、11つ、12つ、13つ、14つ、15つ、16つ。ご馳走さんと立ち去って行きます。
その光景を近くで見ていた男がいました。男は先ほどの男が、1文ごまかしたのに気づいたのです。そして自分も試したくなった男はあくる日細かい銭を持ち、そば屋に向かいますが・・・
蕎麦噺はこちらもおすすめ!「そば清」

粗忽長屋
粗忽(そこつ)とは、そそっかしい、軽率で慌てん坊などの意味合いがあります。
立川談志さんは、主観性が強すぎた為、自分自身が死んだのかという事さえも正しく判断出来なかったとしています。その為立川談志さんは主観長屋として演じていました。
慌てん坊の粗忽な八五郎とおっとりとした粗忽な熊五郎の奇妙で不思議なお話しです。
あらすじ
ある日、八五郎は道端に人だかりが出来てるのに気づき近づいてみると。昨晩、身元不明の行き倒れが出たので、通行人に死体を見せて、知り合いを探しているのだという。
八五郎は死体を見るなり、これは同じ長屋の熊五郎だと言います。今朝調子が悪いと言っていたからという八五郎に、役人は、この行き倒れが死んだのは昨晩の事だからお前の言っている男とは別人だと言うのです。
八五郎は役人の言葉に聞く耳を持たず、今から本人を連れてくると言い残しその場を立ち去ります。
長屋に着いた八五郎は、熊五郎に、浅草寺の近くでお前が死んでいると伝えます。何を言ってる、俺は今ここで生きてるじゃないかと熊五郎は言いますが、お前は粗忽者だから、自分が死んだ事に気がつかないんだ、などと言われてるうちに、自分は死んだのかと納得してしまう熊五郎。
そして、八五郎に連れられ浅草観音まで熊五郎は向かいますが・・・
まとめ
今回の2つの演目は、多くの噺家さんが演じているので、色んな噺家さんの話を聞いて色の違いを楽しんで頂きたく選びました。
同じ演目でも、こんなにも違う話のように演じる噺家さんの凄さを感じて頂けると思います。
題名で古典落語のあらすじを検索出来ます!隠れた名作を見つけて下さい!