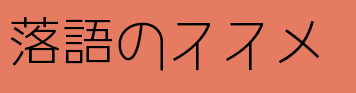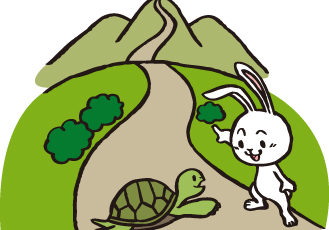本日は古典落語の中でも一風変わったお話を一席ご紹介したいと思います。
「首屋」という演題が付いているのでちょっと怖い話のような感じもしますが、怖い話どころか馬鹿馬鹿しい話ですのでご安心下さいませ。
古典落語 首屋
江戸時代には今では考えられないような商売が沢山あったそうです。
落語の世界でもその風変りな商売を題材にした噺がいくつかありますが、この「首屋」もその一つ。
首屋という名前の通り首を売る訳ですが、動物の首でも他人の首でもありません。自分の首を売りに出しているのだから訳が分かりませんよね。
以前、ご紹介したあくびの仕方を教えるといった「あくび指南」もそうですが、落語には昔ならではの商売を題材にした作品がいくつかありますので、あわせてそちらもご覧になるとより一層古典落語が楽しめますよ。
あらすじ
「くび~。首屋でござい~。首、首はいらんか~」
風呂敷包みを一つ背負った男が、売り声をあげながら番町までやってきた。
今までどこを売り歩いても声すら掛からなかった男だったが、このあたりは旗本屋敷が多かった事もあり、その売り声を聞いた殿様が興味を示します。
「これ、三太夫。世の中には変わった稼業があるものだな。首を売りにきたぞ」
「いやいや。殿。恐らくお聞き違いかと。恐らくは栗屋ではないかと」
「いや。。確かに首屋と申しておる。もし首なら求めようと思うので、調べてまいれ」
三太夫が商人を呼び止めて、話を聞くと本当に首屋で自分の首を売ると言う。まさかと驚く三太夫だったが、そうであれば殿様が求めているので、わしと一緒に入り庭先に控えていろと伝えた。
首屋が庭にしゃがんでいると、殿様が縁側に現れ、どうして首屋などをやっているのかと聞いた。
「へぇ。これまで何をやってもうまくいかないもんで。。首でも売ったほうがいいかと」
値を聞くと七両二分だと言う。江戸時代では、間男の示談金が七両二分だった為、それでは首代は身寄りの者に届けようと殿様が言えば、いえ自分が頂戴するとの答え。
自分の首がなくなるのに金をもらっても意味がない。しかし、首屋は地獄の沙汰も金次第というので、金があった方がいいなどど呑気な事を言っている。
面白い奴がいたもんだ、殿様は三太夫に七両二分を払わせると、覚悟は決まったか?と問いかけた。
「へぇ。ただもういっぺんだけ娑婆を見たいので潜り戸を開けてもらえないでしょうか?」
いいだろうと潜り戸を開けたまま、殿様が白鞘の刀を手に庭に降り、ひしゃくの水を鍔ぎわから切っ先までかけさせます。
「覚悟はよいな」
殿様が刀を打ちおろした。その瞬間、首屋はひらりと身体をかわすと風呂敷から張子の首を放り出して潜り戸から逃げ出した。
「貴様!これは張子ではないか!買ったのは貴様の首だ!」
「へぇ。こっちの首は看板でございます」
古典落語あらすじ検索 難しい落語にはサゲ(落ち)、解説を入れています
題名で古典落語のあらすじを検索出来ます!隠れた名作を見つけて下さい!
古典落語の名作はまだまだ他にも!